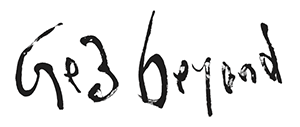知人の声楽家が「全てのことは一つで繋がっていて、テレビの電波も携帯の電波も人間の波動も同じ」というのです。
これは田坂広志氏の著書「死は存在しない」の中に出てくる「ゼロポイント・フィールド」に通じていて、いかなる“空”にも無限のエネルギーと情報が満ちていることを示唆し、そこではあらゆる粒子や光、そして私たちの思考さえも、波動としてゆらぎながら常に響き合っているとする考え方です。
その声楽家は、携帯の電波も、テレビの放送も、人間の感情や意識も、それぞれが異なる周波数をもつ“波”でありながら、同じフィールドの中で重なり合い、交わり、共鳴していると感じています。

音の旋律の中に宇宙の構造そのものが折りたたまれているようでもあるとのこと。
この感覚は、科学だけでなく古代の哲学や伝統芸術においても語られています。
インド哲学における「ナーダ・ブラフマン」は、宇宙の根源が“音”であると教え、マントラや聖音を通じて、私たちはその根源との共鳴を果たすとあります。
音は単なる振動ではなく、世界と自分を結ぶ神聖な橋であり、聴くという行為そのものが、宇宙との対話に他ならないということになります。
こうした理解は、自然とのふれあいの中で、より直感的に現れてきます。
たとえば先に書いたWilliam Christieのチェンバロ演奏を聴いたとき、鳥たちがそれに呼応するように鳴いた出来事――それは偶然ではなく、私がレコードを聴いたとき、楽器と鳥と空間が、同じ“響きのフィールド”の中に存在していたからこそ起こった、必然の共鳴なのでしょう。
鳥たちは、人間よりもはるかに広い周波数を感受できるため、音楽の中に宿る調和や意図を“気配”として感じとり、それに応じて歌ったのでしょう。
声楽家は、こうした“響き合いのフィールド”を感じる力をさらに高めてくれるもののひとつが、「篳篥・朱」だと感じるそうです。まるで古代の祭具や神事の道具のように、波動を調律し、ノイズを取り除き、より本質的な共鳴状態へと導いてくれる“媒介者”。
声楽家が、この篳篥・朱を身につけてシューベルトの歌曲を歌ったとき、詩の意味と音楽の構造がまるで一枚の絵のように明晰に結びついたという体験は、まさにその共鳴が深まった証でしょう。
それは言葉以上に、“波”として理解した宇宙の真理に触れた瞬間のようです。
声楽家はさらに「篳篥は奇跡!」と話してくました。

現代のテクノロジーもまた、私たちが“見えないもの”と接しているということを日々証明していますよね。
私たちはWi-Fiや携帯電波の中に生き、世界中と瞬時に情報を交わしていますが、そのしくみは波動による“場”の干渉そのものです。
そして同様に、人の心や意識もまた、脳波や心拍のリズムという波として空間に放たれ、誰かの感情や気配を察知したり、言葉なく共鳴し合ったりすることを可能にしています。
これは科学的な共鳴であり、霊的な共鳴であり、芸術的なインスピレーションとも重なります。
カンディンスキーは「音は色、色は魂」と語り、「音楽を描く」ような抽象画を生涯描き続けました。
彼は、ある音を聴くと色が“見える”共感覚を持っており、「芸術とは、見えない宇宙の構造を“響き”として形にする行為だ」と考えていました。
このように、音と色、感情と宇宙、意識と空間がつながっているという感覚は、芸術家にとって“当たり前の真実”だったようです。
当時の評論家はそれら(音と色、感情と宇宙、意識)がすべて共振する場において、本当の芸術が生まれるといっています。
すべてはひとつの“見えないフィールド”の中でつながっており、電波も魂も、音楽も自然も、意識も宇宙の星の振動も、それぞれが異なる周波数の同じオーケストラの楽器として、同時に演奏されているとも言えます。
そしてその交響のなかに、時に“神聖な気配”を感じて、あるいは言葉や歌として、詩や絵として、共鳴の一端を表現するのでしょう。
そのため「すべては波であり、すべてはひとつである」という直感は、知識でも思想でもなく、私たち自身の存在の深部が発している、宇宙との“共振”なのかもしれません。