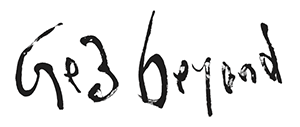過日お会いした佐藤豊彦さんが「楽器には誰かが住んでいる」とおっしゃっていました。
これは、演奏家たちのあいだでしばしば語られる言葉です。
その一言の中には、ただの詩的な比喩では語り尽くせない、深い実感と真実が込められています。
そして同時に、「では、オーディオにも誰かが住んでいるのか?」という問いが、私たちの心に静かに差し込んできます。

それは、音楽と人、物と魂の関係を根源的に見つめなおす問いだと思います。
熟練の演奏家たちはしばしば、長年弾き込まれた楽器、特にストラディヴァリウスやガルネリのような歴史ある銘器に、明らかに「気配」を感じると言います。
ヴァイオリン、チェロ、ピアノ、チェンバロ――これらの楽器は、もはや“道具”ではなく、生きている「存在」として接されます。
木が呼吸し、弦が語り、共鳴胴の奥から「かつてその楽器に命を吹き込んだ奏者たちの想い」が立ち上がってくるように感じられるのです。
ある楽器に触れたとき、まだ弾いてもいないのに、どこかで“目覚めた”ような気配を感じることがあります。
まるで、そこに潜んでいた「誰か」が、こちらを見ているかのような瞬間。
その感覚は、単なる物理的な共鳴や音の美しさでは説明しきれない、「魂との対話」とでも呼ぶべきものです。
このような感覚は、オーディオ機器にも確かに宿ることがあります。
優れたアンプ、スピーカー、丹念に調整されたプレーヤー……
これらは単に電気信号を音に変えるだけの「装置」であるはずなのに、そこから流れる音楽を耳にすると、まるで“誰かがその場で演奏している”ような錯覚にとらわれます。
良質なオーディオの中で音楽が再生されるとき、それは単なる「再現」ではなく、「再生(よみがえり)」なのだとさえ感じられます。
空間を満たす音の中に、演奏家の吐息、指の動き、心の震えまでが蘇り、今ここで“生きている”ように響いてくるのです。
そこに聴こえるのは、物理的な音だけではありません。
音に混じって、「気配」や「記憶」や「祈り」が、確かに漂っている。

では、その“誰か”とはいったい誰なのでしょうか?
それは、録音された演奏家の魂の残響かもしれません。
あるいは、作曲家がその旋律に託した想念。
あるいは、オーディオ機器という器に“宿ってしまった”精霊のようなものかもしれません。
しかし、哲学的に言えば、その「誰か」を感じさせているのは、実は聴いている私たち自身の“感受性”かも知れません。
人は、美しいものに出会ったとき、そこに命を見る力を持っています。
風が木を揺らす音に神を聴いた古代の人々のように、私たちは音楽や楽器、オーディオの中に「生」を感じ取る。
そして、ただの木材や金属のはずのそれらが、「何かを受け取る器」となり、そこに“誰かが住んでいる”と感じさせるのです。
私が「Pancrace Royer」のチェンバロ録音を聴いたとき、音が教会の空間に満ち、その余白に鳥の声が呼応した。
この体験は、ただ音を聴いたというだけでなく、「世界が音に耳を澄ませていた」ような感覚になりました。
鳥たちが音楽に呼応し、沈黙さえも音と共鳴しているような瞬間。
その時、きっと、そこには演奏家の存在だけでなく、音楽そのものの“魂”が、空間に立ち現れていたのだと思います。
このような体験をしたあとでは、もはやオーディオも楽器も「ただの物」ではありません。
それらは人間の手によって生まれ、感情を伝えるために作られ、使いこまれ、そして、いつか“魂を宿す器”になります。
真空管アンプの淡い光、スピーカーの振動、レコード針のかすかなノイズ。
そのすべてが、音を生む「生き物」として、私たちに静かに語りかけてきます。
だからこそ、私は問いかけてしまいます」。
「この楽器には、誰が住んでいるのだろう?」
「このオーディオの中で、今、誰が演奏しているのだろう?」
その問いは、きっと音楽の本質に近づくための扉なのかもしれません。
音を聴くということは、音の中に誰かを感じること。
そして、その“誰か”と、魂のどこかで対話することだと思います。