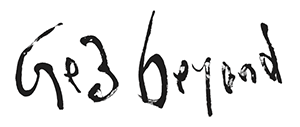一昨年の11月「篳篥・朱」の販売相談で、元サントリーホール(現職サントリーグローバルイノベーションセンター)の林さん、フランス人ジャーナリストのドラ・トーザンさんらに霞町音楽堂でお会いしました。
その日、お二人の紹介でチェンバリストの高野 凛さんとお会いし、篳篥を使っていただきました。
彼女にいろいろな話を伺っていると、彼女のお母様の高野美佐子さんはリュート奏者で、世界的なリュート奏者の佐藤豊彦さん※のお弟子さんとのこと。
私は佐藤豊彦さんの大ファンで、作曲家と繋がろうとする彼ら古楽演奏家のレコードをよく聴きます。
佐藤豊彦さんは、作曲家に想いをよせる古楽器演奏家でオランダ王立ハーグ音楽院の教授で、世界的な古楽器演奏家でリュート奏者です。
古楽器演奏家は、作曲家の時代の音程や曲のテンポを研究し作曲家と対峙し作曲当時の演奏を尊重します。
そのためリュートが演奏された、約400年前の楽器を使います。
私は、高野美佐子さんとFacebookで繋がることができ、今年、佐藤豊彦さんが東京でリサイタルをすることをお知らせいただきました。
当日会場で高野美沙子さんを尋ねると、そのまま楽屋に案内いただき、憧れの佐藤豊彦さんを紹介いただきました。
一昨年、高野 凛さんにお会いした時、ぜひ高野美佐子さん、佐藤豊彦さんに「篳篥・朱」をお渡しいただけるようお願いしていました。
その後、佐藤豊彦さんに「篳篥・朱」は届いているのかどうか、ホームページやfacebookを通じで、連絡を試みていたのでがお返事はいただいていませんでしたので、どうご挨拶しようかと思案していたら…
ところが、ご挨拶をすると「篳篥は凄いね!レコーディングに使ったよ。」とおっしゃるのです。
佐藤豊彦さんはご自身で篳篥の使い方を模索されたそうで、リュートの糸巻きに挟んで使用されていたとのこと。
「篳篥・朱」をほとんどご存知ない状況で、何かを感じていろいろ使い方を試されたそうです。
その想像力に本当に驚かされます。
佐藤豊彦さんの活動はオランダを中心とされていたので、生で聴かせていただくのは初めてです。

リサイタルは短いレクチャーから始まりました。
1曲目エルンスト・ゴットリープ・バロン作曲、組曲 b Major。
その1音目の音がリュートから弾かれた瞬間、このコンサートホールから、バロック期のドイツなのか佐藤豊彦さんの世界の中なのか、タイムスリップしました。
リュートの弦の振動を感じると、その周りに空間があって、何か魂のようなものを感じて他の世界にいざな割れたようです。
400年前の空気を感じました。
佐藤豊彦さんとのご縁は、篳篥・朱に助けられたようです。
私たち音楽愛好家は演奏家とつながり、演奏家の演奏によって作曲家にもつながることができる。
演奏家は「篳篥・朱が天使を呼んで、楽器とつながる手助けをしてくれる」と言い、さらに
「天使が作曲家ともつなげてくれる。』」と言います。
すごいリサイタルでした。(つづく)
※現在熊本県の荒尾市に在住。
立教大学在学中、当時ヨーロッパから帰国間もない皆川達夫の西洋音楽史を受講、それを機に1968年スイス、バーゼルに留学、オイゲン・ドンボアにリュー トを師事。
1971年に世界で初めてのバロックリュートLPを録音してデビュー。1973年、29歳でオランダ王立ハーグ音楽院の教授に就任、2005年 に退官するまでの32年間、現在世界各国で活躍する多くのリュート奏者を育てた。
1982年のカーネギーホールでのリサイタルは、ニューヨークタイムズに 写真入で絶賛を博した。録音ではToshiba、Telefunken、Philips、EMI,、Channel Classics、Carpe Diem、Nostalgia、レーベルで数多くのLP、CDをリリース。
1980年オランダ・エジソン賞、同年に日本で文化庁芸術祭賞、1983年と 2008年の2回にわたってレコード・アカデミー賞他受賞多数。
著作物では「バロックリュート教則本」、「ヴァイヒェンベルガー・リュート選集」、「歌 曲、或いはエア集 第1巻」などがある。
2000年「リュート&アーリーギターソサエティ・ジャパン」(LGS-Japan)を創立。