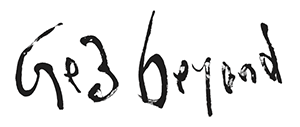5月7日 NHK BSで放送された「フロンティア」という番組、
この日の特集が「人はなぜ歌うのか?」、
音楽の起源の答えを求めてアフリカの熱帯雨林に住む
「バカ族」を取材しています。

「人はなぜ歌うのか?」
きさ@Ge3とたまに話題にしていますが、
今世紀に入って研究者の間で議論が交わされている“難問”だそう。
「バカ族」は、アフリカ中部のカメルーンのほか、
コンゴ共和国や中央アフリカ共和国などの
熱帯雨林に暮らす狩猟採集民です。
一説によると「バ=人」「カ=葉っぱ」で、森の民という意味だとか。
バカ族は美しい音楽を生み出す「音楽の民」として知られています。
私は以前、フランスのOCCORAというレコード会社の
「カメルーンの音楽」を聴いて美しい和音と複雑なリズムに驚きました。
4小節をひたすら繰り返す、今で言うラップです。
私は、ラップは音楽でもあるけれど、
意見を共有する世代のコミュニケーション・ツールだと思っています。
番組では、バカ族が「音楽の起源」の謎のカギを握っているのではないか。
研究者たちがそう考えるのには、大きく2つの理由があると言っています。
(1)バカ族の暮らしでは「音楽が言語よりも大事」な意味を持つ
(2)バカ族は「10~20万年前のDNA(もしくは遺伝的特徴)」を色濃く残している
最新のゲノム解析などによって、バカ族は10~20万年前の人類から枝分かれし、
長らく孤立した森の環境で暮らしてきたことがわかってきました。
遠い祖先がアフリカの熱帯雨林で狩りをして暮らしていた頃の音楽の姿が、
そこにあるのかもしれません。
洗濯をする時、木に登る時、狩をする時、
お互いが音楽で自由にコミニケーションしている
そんな世界があるとしたら、
求めている答えに近づけるかもしれない。
バカ族では女性が歌い、男性は太鼓や木を叩いたりするのが基本だそう。
複雑なメロディーとリズム、短いフレーズが繰り返されて、
どんどん場の空気が温まってきます。
妖精が集まって来ているのでしょうか?
「踊りだしたくなるようなグルーブ感!」絶頂に達しようとする手前、
唐突に歌が終わり、みんな何事もなかったかのように日常に戻っていきます。
番組を見ていて呆気に取られます。
取材者は..
「彼らの音楽はいつも最高潮に達するちょっと手前で止めて、時間がまた流れていく。
また誰かが手を叩き始めると、また音楽の時間が始まる。
それの繰り返しでちょっとずつ音楽的時間が増えていって、
徐々に熟成してコミュニティーの音楽をみんなで作っていく感じなんです」
と語っていました。
バカ族が歌う美しい「ポリフォニー」は1970年代頃から、
現地を訪れた研究者たちの録音物によって
世界の音楽ファンに知られていきました。
「ポリフォニー」とは、異なるメロディーを複数の人たちで
同時に歌って作り出す複雑な歌のこと。
バカ族の間では「皆で歌うことを『ベ』といいます。
バカ族は言葉ではなく歌で、仲間になろうと望まれていることを理解します。
森の精霊だって歌を聞くと『ベ』に呼ばれているんだなと思って、
森から出てくることがあるそう。
私は、この感覚に深い興味を覚えます。
さらに取材者は…
バカ族の人たちと生活していると、
女性たちが水浴びや洗濯の時に川面を叩いて複雑なリズムを生み出す
「ウォータードラム」、夜の民話語りの歌「リカノ」など、
日常の折々で「べ」に出会いました。
「一番大事な歌」と言われていたのが「イエリ」。
男たちが狩りに出かけた時に獲物が獲れるように歌う歌です。
と語っています。
暮らしの中で即興的にポリフォニーを歌い、
それがコミュニケーション手段として重要な意味を持っているバカ族の人たち。
彼らにとって、歌でコミュニケーションする相手は人間だけではなく、
「イエリ」は森と動物の心を柔らかくする力があるのだといいます。
音楽的に面白かったのは、
バカ族の人たちはいつもみんなで歌います。
なぜなのでしょうか。
番組では、ポリフォニーの構造を分析して、その理由を探っています。
ポリフォニーに参加する7人の女性の歌声を別々のマイクで収録。
すると以下の二点が分かりました。
(1)全員が違うメロディーを歌っている
(2)それぞれのメロディーを重ねてみると「完全4度」の音の重なりが完成する
楽譜もなしに即興で美しいハーモニーを 作り出しているのは驚きです。
さらに、バカ族の歌で特徴的なのは「複雑なリズム」が生むグルーブ感!
沖縄県立芸術大学非常勤講師 古謝麻耶子さんによると
「きっと彼らは初めて習得する時から全体の中の1人として参加していて、
人とは違う歌を歌い続ける、ずらしたリズム、
むしろ他の人がやってないことを自分がやる。
そうすることで、より緻密で満たされた歌のあり方を目指しているのではないでしょうか。
もしかしたらそれが彼らの社会や生き方とも繋がってくるのではないかと感じました」
ノースイースタン大学 サイキ・ルイ博士は、
音楽のビート(リズム)を聴くと、
脳内でドーパミンなどの報酬物質が発生することがわかっています。
報酬物質とは私たちが気持ち良さ、
快楽を感じた時に分泌される脳内物質です。
ビートが繰り返されると脳の「予測機能」が働き出し、
次にどんなビートが来るか「予測」し始めます。
予測することの快感に加え、裏切られることの快感もあります。
予測の複雑さを脳が喜んで大きな報酬を感じると言います。
番組では総括として
コミュニケーションの音楽=集団の絆として、
音楽の起源を考える上で外せないとしています。
音楽のビート(リズム)にはたくさんの人を同時に動かす力があります。
他人と一緒に体を動かすことは同じ体験の共有です。
共に歌うのは『助け合えるよ』というサインだと言ってもいい。
社会的動物であるヒトにとって報酬を感じる行動です」
としました。
番組のぶら下がりで、
アムステルダム大学 ヘンキャン・ホーニング博士に聞いています。
「動物はグルーミング(毛づくろい)で『集団の絆』を確認しますが、
ヒトが作った大集団ではグルーミングしきれない。
その代わりに音楽が生まれたのではないでしょうか。
集団が協力し合うためにとても役立つ発明だったはずです。
『ヒトはなぜ歌うのか?』の答えは『集団の絆』のため、
私たちは人とつながるために音楽を手にしたといっていいのではないでしょうか」
面白い番組でした。
音楽は化石にならないけど、記憶に残ります。
「言葉は消えても 音楽は残る」という事です。
カメルーンのバカ族は「精霊は音楽が好き」と言っています。
学者は、「リズムを複雑にして、それを理解すると脳が喜ぶ」
「音楽は、複雑に出来たことで報酬系になる」
「コミュニティーへの参加を実感する」
「コミュニティーでの存在意義を感じる」
と言います。
音楽の起源には、そこに妖精の助けがあるかどうかで、
残る音楽とそうでないものがあるように感じます。
Ge3の製品作りのポリシーに深く関係している事です。